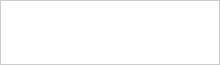ルカの福音書24章を見て行くと、弟子たちがキリストの復活という真実を受けとめて行く過程が丁寧に描かれていることがわかる。彼らはすぐにキリストの復活を信じたのではない。夜明けとともに日の光に照らされて辺りがだんだん明るくなっていくように、彼らは信じるようになっていく。24章はいわば彼らの黎明期の物語である。
日曜日の早朝、女弟子たちが墓に向かった(1節)。墓は空であった。御使いたちから主イエスはよみがえられたという告知を聞く。また御使いから、主イエスが生前、十字架とよみがえりについて話されていたことを思い出しなさい、ということばを聞く。彼女たちは、主イエスのおことばを思い出す(8節)。彼女たちはこれらの出来事を使徒たちに報告する。だが、使徒たちたわごとと思ってしまう(11節)。「たわごと」は、馬鹿々々しいこと、ナンセンスを意味することばである。ペテロは彼女たちの報告を聞いて墓に向かう。墓はやはり空であった。その時のペテロの反応は驚いたということである(12節)。「驚く」ということばは「不思議に思う」という意味であるが、この驚き止まりで、まだ謎は解けない。ペテロはその後、34節で「本当に主はよみがえって、シモン(ペテロ)に姿を現された」とあるように、復活のキリストと出会うという体験をし、ようやく信じたようである。そして、エマオの途上の弟子たちも復活のキリストと出会うことになる。
先週は、エマオの途上でクレオパともう一人の弟子が復活のキリストと出会うという体験を学んだ(13節以降)。彼らは旅の同伴者から、旧約聖書がキリストについてどのように語っているのか、その聖書の説き明かしを聞き、その後、同伴者が復活のキリストご自身であると悟ることになる。彼らは、エルサレムに戻って、この体験を使徒たちに話すことになる(35節)。その前に33,34節からわかるように、ペテロも復活の主と出会った体験を彼らに語ったようである。「二人はただちに立ち上がり、エルサレムに戻った。すると、十一人とその仲間が集まって、『本当に主はよみがえって、シモンに姿を現された』と話していた」。そのさなか、エマオの途上の弟子たちが戻って来て、自分たちの体験を話すことになる。しかし他の弟子たちの心はまだ鈍いままであった。信じたようでそうではなく、まだ半信半疑である。
今日の記事は、主イエスが使徒たちが全員そろっているような場所で顕現してくださったという内容である。使徒たちは復活の証人となるべく召された人たちであったので、全員が主イエスの復活を確信する必要があった。
主イエスの顕現の場面を見よう。「これらのことを話していると、イエスご自身が彼らの真ん中に立ち、『平安があなたがたにあるように』と言われた」(36節)。主イエスは彼らの話の最中、その話の場の真ん中に出現した。ドアを開けて、そこをくぐって部屋に入ったというのではない。では幽霊なのか?そうでないことは、この後、証明される。「平安があなたがたにあるように」というあいさつ自体は、「おはよう」とか「こんにんちわ」に相当する、ユダヤの日常のあいさつ用語である。だが、ヨハネ20章19節以降の復活物語を見ると、このあいさつのことばを三回も使っておられる。だから、これは単なるあいさつのことばとは思えない。メシアが与える平安という意味合いが強いだろう。ヨハネ20章19節ではこう言われている。「その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちがいたところでは、ユダヤ人を恐れて戸に鍵がかけられていた。すると、イエスが来て彼らの真ん中に立ち、こう言われた。『平安があなたがたにあるように』」。恐れ、委縮、不安、混沌とした思いがあった。だから、なお彼らには平安が必要であった。
ところが彼らは、別の意味で恐怖にかられてしまった。「彼らはおびえて震え上がり、幽霊を見ているのだと思った」(37節)。彼らは喜びに満たされ飛び上がったのではない。おびえて震え上がってしまった。主イエスは彼らの様子を見て語りかける。「そこで、イエスは言われた。『なぜ取り乱しているのですか。どうして心に疑いを抱くのですか』」(38節)。主イエスは彼らの反応から、「疑い」ということを読み取っている。主イエスの復活を信じるということは、彼らにとって容易なことではなかった。十字架刑の前に、三日目によみがえるという預言をご本人の口から何度も聞かされていた。そして、女弟子たちから空の墓の復活物語を聞かされた。他の福音書では、彼女たちの前に復活の主が現れたことが書いてある。この体験も聞かされたであろう。弟子の筆頭であるペテロからも聞かされた。クレオパたちからも聞かされた。復活の主と会いましたという報告を見知らぬ人たちからではなく、何人もの親しい仲間たちから聞いた。しかもそれは時間差がある別々の複数の体験だった。彼らは熱弁を振るって自分たちの体験を話しただろう。本当にお会いしたのだと。にもかかわらず、半信半疑を超えるまでは至らなかった。そして、いざ復活の主が目の前にお立ちになると、幽霊だと反応してしまった。ご本人が目の前に顕現しているのに、使徒たちはなかなかスッキリと信じられない。主イエスは魚まで食べてみせることになる。さらに、ヨハネ20章では、使徒のトマスが最初の出現の場面にいなかったので、他の弟子たちが「私たちは主を見た」と言っているのに、トマスは「私は、その手に釘の跡を見て、釘の跡に指を入れ、その脇腹に手を入れてみなければ、決して信じません」と疑いを言い表したことが記されている(20章25節)。さらに、マタイ28章では、ガリラヤの山に大勢の弟子たちが集まって、復活の主を礼拝している場面で、「ただし、疑う者たちもいた」(28章17節)と記されている。これは、使徒たちは全員信じたけれども、他の弟子たちの中にはまだ疑う者もいた、という記述である。聖書は正直に、キリストの復活をなかなか信じられない弟子たちの不信仰、心の鈍さというものを描いている。
主イエスは続けて言われる。「わたしの手やわたしの足を見なさい。まさしくわたしです。わたしにさわって、よく見なさい。幽霊なら肉や骨はありません。見て分かるように、わたしにはあります」(39節)。主イエスは「見る」ということばを三回も使って、「見なさい」と強調している。眼(まなこ)を開いて良くみなさいと。「まさしくわたしです」と、わたし以外の何者でもないと訴えておられる。「まさしくわたしです」という表現は、原語において、可能な限りの強い断言のことばになっている。疑う余地を一パーセントも与えまいとすることば。百二十パーセントわたしなのだと相手に迫ることばである。主イエスは「わたしにさわって、よく見なさい」と、さわることも語っておられる。視覚にも触覚にも訴えておられる。肉や骨があることを確かめなさいと。初代教会時代、グノーシスという異端が発生するが、彼らは、イエスは肉体を持っているように見えただけだとも語った。だが違う。主イエスは現実に肉と骨をもっておられる。肉と骨があってからだと言えるのであり、主イエスの復活のからだは現実のものであったのである。それをさわって確かめよと。わたしには肉と骨があるよと。「こう言って、イエスは彼らに手と足を見せられた」(40節)。使徒ヨハネは後に、ヨハネの手紙の第一の序文を、「初めからあったもの、私たちが聞いたもの、自分の目で見たもの、じっと見つめ、自分の手でさわったもの、すなわち、いのちのことばについて」(第一ヨハネ1章1節)という書き出しで始めることになる。ヨハネは復活の主を見て、さわった体験を前提に、主イエスの紹介を始めている。
さて、この後の弟子たちの反応だが、「彼らが喜びのあまりまだ信じられず、不思議がっていた」(41節)とある。喜びという感情が湧いてきたが、「まだ信じられず」ということばが続いている。まだ信じられない。「不思議がって」ともある。これをどう理解したら良いだろうか。たとえは悪いが、息子が戦地に取られ、息子の戦死の通知が届いて悲嘆に暮れていた時、ただいまと言って、息子が玄関に立っていたらどうだろうか。最初は半信半疑で現実のこととは思えないだろう。夢を見ているのではないだろうか???喜びと疑いが入り混じった独特の心境を通過するはずである。弟子たちもそのようであったのではないだろうか。
主イエスは彼らの疑いに終止符を打つために、ユニークな行動に出る。「イエスは、『ここに何か食べ物がありますか』と言われた。そこで焼いた魚を一切れ差し出すと、イエスはそれを取って、彼らの前で召し上がった」(41節後半~43節)。皆の視線は主イエスに注がれたであろう。当時は、御使いも幽霊も食事をしないというのが通念としてあった。これが前提としてある。けれども、主イエスは食事をされた。皆の視線を浴びながら。ハタハタを食べなかったことは確かであるが、主は確かに魚を食べられた。主イエスはからだをもって復活されたのである。こうして、主イエスの復活を疑っていたことは、後の思い出話になっていったのである。
彼らにとって主イエスの復活を信じるというのは実にハードルが高かった。よって、主イエスの復活を信じるのには、様々なプロセスが必要となった。空の墓を目撃することや、主イエスが語られたみことばを思い出すことや、復活の主と出会ったという人たちの証言を聞くことや、そして実際、からだをもってそこにおられる主イエスを自分たちの目で見てさわることや、食事する様子を見ることによって。そこまでして、ようやく疑いは消え、確信をもって信じるに至った。復活は使徒たちをはじめとする初代教会の人たちの作り話とする人たちがいるが、使徒たちでさえ信じるのにかなりまごついたという事実が、復活作り話説を一掃する。ユダヤ人たちを恐れて部屋にこもっていた者たちが、自分たちの作り話のために命をかけるようになるなどというのもばかげている。
今日は、使徒たちがキリストの復活を信じるまでの過程を観察してきた。最初は完全な不信の状態であった。その後、女弟子やペテロやエマオ途上の弟子たちからの証言を聞いても、何かまだ信じられない。主イエスが顕現されても、目の前にしても、まだ半信半疑で、疑いはしつこかった。主イエスは彼らの疑いを取るために、サービスとして魚を食べるというパフォーマンスまでしてくださった。弟子たちは旧約聖書を読んでメシアの働きを悟っていたら、もう少し早く信じることができただろう。また主ご自身から何度も聞かされていた、三日目によみがえるという復活の預言を真摯に受け止めていたら、ここまで右往左往しなかっただろう。主イエスはエマオ途上の弟子たちに対して、「ああ、愚かな者たち。心が鈍くて、預言者たちの言ったことすべてを信じない者たち」(25節)と言われたが、それは使徒たちも同じであった。当時の律法学者たちもそうであった。律法学者たちは人の言い伝えに聖書と同じ権威を与えてしまったために、聖書を読みそこない、自分たちの伝統に立てつく主イエスをメシアとさえ思っていなかった。バプテスマのヨハネでさえ、主イエスがメシアであることを一時疑い、「おいでになるはずの方は、あなたですか。それとも、ほかの方を待つべきでしょうか」(7章19節)と、自分の弟子たちに言づけて尋ねさせたことがある。ヨハネのメシア観は、出現したら、すぐにでものさばる悪に審判を下してくださるお方ということがあった。だがその気配はなく、それどころか、自分はヘロデ・アンティパスによって、死海の近くにある山の頂の狭い石牢に閉じ込められたままで、数か月が経っていた。主イエスはヨハネに対して、わたしはいやしのみわざなど、聖書のメシア預言どおりの働きをしていると伝えるよう指示した。使徒たちの場合、主イエスがメシアであると信じていたからこそ、付き従っていった。だが十字架の死は、彼らを絶望の淵に突き落とした。彼らの聖書理解もまた足りなかった。私たちも聖書の信じたいところだけ信じて終わっていないだろうか。色眼鏡で聖書を読んでいないだろうか。そのようにして、キリストの姿を矮小化したり、キリストの働きを削ったり、ゆがめたりしてしまっていないだろうか。だが現状では、そうした信仰者は多くいる。復活に限ると、「キリストが本当に復活したかどうかが問題ではない。弟子たちの心の中にキリストは生きている。そのことが大切なのだ」という煙に巻く話で、キリストの復活をうやむやにする人たちもいる。だが、復活は煙に巻いて終わらせるたぐいのものではない。それは信仰の土台である。パウロは言っている。「キリストがよみがえられなかったとしたら、私たちの宣教はむなしく、あなたがたの信仰も空しいものとなります」(第一コリント15章14節)。死人で終わった人物を信じて、何の望みがあるだろうか。
自分をメシアと名乗る者、キリストと名乗る者は、主イエスの後も、軽く100名は起こされただろう。だが復活されたのは主イエスのみである。だからこそ、このお方こそ真のメシア、救い主なのである。復活こそ真のメシアのしるしであると悟らなければならないのである。