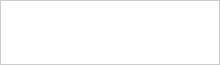ルカの福音書の復活物語において、復活されたキリストのお姿を最初に書き記した記事が今日の物語である。前回は1~12節より、日曜日の早朝に女弟子たちが墓に向い、墓が空であるので途方に暮れていたところ、御使いたちから主イエスがよみがえられたという告知を聞いて墓から戻り、男弟子たちに報告したけれども、男弟子たちはたわごとと思って信じなかったことを学んだ。また、ペテロは墓に行ったけれども、空なので驚いたというところまで学んだ。彼らの信仰には霧がかかっていた。4節の「途方に暮れる」は、困惑するという意味のことば。11節の「たわごと」は馬鹿々々しいという意味のことば。12節の「驚く」は不思議に思うという意味のことば。どの反応にしても、主の復活を信仰をもって受け止めきれないでいる心の鈍さから来ている。彼らは、主イエスご自身の口から何度も、三日目によみがえるということばを聞いてはいた。旧約聖書も、メシアが死で終わってしまうとは書いていない。
今日の記事ではエマオ途上の二人の弟子が登場するが、やはり心は鈍く、みことばに心が開かれていなかった。「そこでイエスは彼らに言われた。『ああ、愚かな者たち。心が鈍くて、預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たち』(25節)。彼らの心はみことばに対して閉ざされていたので、他の弟子たち同様、表情が沈んでいた(17節後半)。彼らにとって主イエスは死人のままであった。それはうその現実を信じたままでいたということでもある。「不信仰」とは、信じるべきことを信じないことだが、言い方を変えれば、うそを信じたままでいることである。信じていればそれでいいということではない。何をどう信じるかが大切である。死後三日目という時期は、ふつうに考えれば遺体が腐り始める時期で、いよいよ望みがないという時期。彼らは主イエスの遺体が腐り始めていることは信じていても、復活は信じていなかった。信じる内容が大違い。
では、エマオ途上の弟子たちの物語を最初から見ていこう。二人の弟子が、同じ日曜日にエマオという村に向かっていた(13節)。エマオの場所は特定されていないがエルサレムの西側の村であると思われている。エルサレムからの距離はメートルに換算すると、約11キロメートルになる。二人の弟子は誰であるのかということだが、18節に、そのうちの一人が「クレオパ」であると言われている。二人の弟子を紹介する場合に、どちらの名前も挙げるのがふつうなのだが、もう一人の弟子の名前は挙げられていない。クレオパだけを挙げてもう一人を略しているのは、可能性の一つとして、もう一人の弟子はクレオパの奥さんなのだろうということである。ヨハネ19章25節には、主の十字架刑を見守っていた女性に「クロパの妻マリア」が登場するが、彼女の可能性もゼロではない。また、クレオパの息子説もある。もちろん、他の男弟子の可能性もある。彼らは、過越の祭りに合わせ都に上って来ていて、その帰りなのかもしれない。
二人の弟子は道すがら論じ合っていた(14節)。歩きながら宗教上の事柄をディスカッションするのは、ユダヤの理想とされていた。この光景自体は珍しいことではない。彼らの議論の内容は「これらの出来事すべてについて」と言われているが、それはイエスの死にまつわる事柄である。彼らはそれを19~25節で主イエスに向けて話しているので、あとで見ることにしよう。
さて、見知らぬ旅人が彼らに近づき、彼らと同行することになる(15,16節)。彼らは、そのお方が主イエスであるとはわからない。16節で、「二人の目はさえぎられていて」と言われている。そのお方は彼らにとってはまさかの人物なので、彼らには認知できなかったと言ってしまえばそれまでなのだが、「さえぎられていて」という動詞の態は神的受動態といって、神が行為者であることを示すものである。神のなんらかの力が働いて識別できなかったと言えるだろう。
主イエスは、彼らの導き手となることを決め、語りかけられる。「イエスは彼らに言われた。『歩きながら語り合っているその話は何のことですか。』すると、二人は暗い顔をして立ち止まった」(17節)。印象的なのは、復活の主がかたわらにおられるのに、表情が暗いということである。主イエスは、「見よ。わたしは世の終わりまで、いつもあなたがたとともにいます」(マタイ28章20節)と約束してくださった方であるが、私たちもこのお方を見失うということはないだろうか。
クレオパは、かたわらにおられる人物に、疑念の質問を投げかける。「エルサレムに滞在していながら、近ごろそこで起こったことを、あなただけがご存じないのですか」(18節)。「近ごろそこで起こったこと」とは、主イエスの十字架刑とそれにまつわる出来事であるが、その本人に向かって「あなただけがご存じないのですか」と語りかけている。いずれにしろ、主イエスが知らないことなどあろうか。そのお方に向かって、私たちも「あなただけがご存じないのですか」と語りかけてしまうのだろうか。「わたしが見た悲しい出来事をあなたは知らないのですか」、「わたしが落ち込んでいる理由をあなたは知らないのですか」と言ってしまうのだろうか。主はすべてを知っていてくださるのである。真実を知らないのは私たちのほうであったりする。
主イエスはすべてを知りながら、彼らの心の糸を解きほぐし、鈍く暗くなった心に明かりをともし、真実を悟らせるために、「どんなことですか」と、彼らに話しをさせる質問を投げかける(19節)。主イエスは私たちに対しても、「どんなことですか」「あなたはどんなことでふさぎ込んでいるのですか」と聞いてくださるお方である。
二人は、主イエスのことを「力ある預言者でした」という紹介で始めている(19節後半)。中には、この二人の弟子がイエスさまのことを、「主」とも「メシア」とも「神の子」とも呼んでいない、と気にする人もいるが、主イエスはご自身のことを預言者と語られたことがある(4章24節)。またルカの文書である使徒の働きでは、ペテロが主イエスのことを、モーセが出現を預言した預言者であると言っている(使徒3章23節 申命記18章15節参照「あなたの神、主はあなたのうちから、あなたの同胞の中から、私のような一人の預言者をあなたのために起こされる。あなたがたはその人に聞かなければならない。」)。私たちがクレオパたちの話で気に留めなければならないのは、主イエスの呼称(呼び名)の問題ではなく、彼らが十字架の死、空の墓、御使いの告知と話を進める中で、24節にあるように、「あの方は見当たりませんでした」で話が終わってしまっているということである。主イエスはミステリーの闇に放り込まれて終わりである。おおミステリー!で終わってしまっている。11節の使徒たちの反応である「たわごと」は「ナンセンス」という意味をもつことばだが、こちらは「ミステリー」という反応と言って良いだろう。いずれにしろ、主イエスは死んだままにされてしまっている。生きているお方ではない。彼らは、女性たちの証言を聞いて、「そうだ、主イエスは生前、ご自分がよみがえることを預言されていた。主イエスはよみがえられたのだ」とはならなかった。彼らは不信仰のゆえに、堂々巡りの議論をしていたのであろう。空の墓の謎は解けないまま。しかも、彼らの中ではまだ主イエスはよみがえってはいない。
そこで、主イエスは彼らにとってのミステリーの謎解きをされる。それは、みことばを示すという方法によった。まず主イエスは、彼らがみことばを信じられないでいることを叱責される。「そこでイエスは彼らに言われた。『ああ、愚かな者たち。心が鈍くて、預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たち。キリストは必ずそのような苦しみを受け、それから、その栄光に入るはずだったのではありませんか』」(25,26節)。そして、旧約聖書全体から、ご自分について書いてあることを説き明かされた。「それからイエスは、モーセやすべての預言者たちから始めて、ご自分について聖書全体に書いてあることを彼らに説き明かされた」(27節)。「聖書全体に書いてあること」の「聖書全体」とは旧約聖書のことである。そこには多数のメシア預言が記されている(イザヤ53 詩篇2編7 詩篇16編10節 詩篇110編1 詩篇118編22節 ダニエル7章13,14節 その他多数)。メシア預言は100箇所を超えるだろう。また旧約聖書には、予型や象徴を通して、キリストが描かれている。アブラハムがイサクをささげること、動物のいけにえ、各種の祭り、ヨブが大魚の中で三日三晩過ごしたことなど。旧約聖書の各書にキリストの姿が隠されている。彼らは、主イエスの旧約聖書全体の説き明かしを聞いているうちに、胸が熱くなってきただろう。当然ながら、もっとこのお方と一緒に居て、このお方の話を聞きたいという思いになったはずである。時は夕刻になろうとしていた。
「彼らは目的の村の近くに来たが、イエスはもっと先まで行きそうな様子であった。彼らが、『一緒にお泊りください。そろそろ夕刻になりますし、日もすでに傾いています』と言って強く勧めたので、イエスは彼らと泊まるため、中に入られた」(28,29節)。同行者はもっと先に行きそうな様子であった。この「もっと先に行きそうな様子であった」というのが微妙な表現で、「もっと先に行くことになっていた」とか、「もっと先に行くことを決めていた」といった断定的な表現になっていない。「様子であった」と訳されていることばは「振りをする」という意味のことばである。何か、「一緒にお泊りください」と言って引き止めてくれるのを待っている様子。引き止めてくれなければ先に行く。相手方には「一緒にお泊りください」と声をかける自発性を求めている。その意志を試している。決して、「クレオパさん、泊めてください」と自らは言わない。強制的にお願いはしない。相手の自発的意志を尊重している。そして、二人は「強く勧めた」と書いてある。それで、主イエスは彼らとともに泊まることに決めて、中に入られた。この家はクレオパの家の可能性もあると言われているが、もちろん、そうでないかもしれない。大切なことは「一緒にお泊りください」という意志である。主イエスは私たちに対しても、自発的に意志を働かせてくれることを願っている。「わたしのところにお入りください」と。「夕闇の光になってください」と。
泊まった先で夕食が始まる(30,31節)。宿泊を誘われた人のほうが主人の位置についている。その人物はユダヤのテーブルマナーにのっとり、パンを取り、神をほめたたえ裂き、二人に渡した。これまで何度か与った光景に、彼らの心の目が開かれ、主イエスだと分かった。この時、キリストの復活のリアリティというものを体験したのである。見知らぬ旅の同行者が、よみがえられた主イエスだと分かったのである。それまでの下準備として、聖書のみことばを通して、メシアは復活することを教えられてきた。彼らの心がそれを受けとめた後、心の目の曇りは晴れ、目の前の人物が復活の主であることを認めることができた。彼らの心の目が開かれたこと自体は、神の働きである。31節の「彼らの目が開かれ」の「開かれ」も神的受動態である。
31節後半において「その姿は見えなくなった」とあるが、以外なことであるが、復活の主はご自身を顕現する場面では、実に短時間しかおられない。「大事なことはわたしの肉体にすがることではなく、わたしに対する信仰だ」と言わんばかりに。これは真理である。キリストの肉体を見ることができないので、キリストの像を形造って拝ませようとしたりする人たちがいるが、それは完全に外れている。二人は主イエスが肉眼では見えなくなっても、心の目が開かれていたので、主イエスはよみがえられたという確信と喜びは変わらなかっただろう。彼らはこの後、希望に満ちて、復活の主を宣べ伝えるべくエルサレムに戻って行く(33節)。彼らの足取りは軽やかで、暗い表情も消えていただろう。そして彼らは、復活の主をともに喜び合う交わりの中に入って行くのである。
クレオパともう一人の弟子は、エマオの途上で不思議な旅の道連れを得た。そのお方はご自分のほうから近づいて来られ、同行者となられた。混乱と悲しみの中にある二人にはまさしく天の助けである。彼らはこのお方の語りかけを聞き、このお方に心の中にある悲しみの要因を吐露し、そして、みことばを聞き、最終的に心の目が開かれ、復活の主の現実を体験するに至った。
17節に、「二人は暗い顔をして立ち止まった」とあるが、もうその暗い顔はない。以前、世界大戦時にドイツの捕虜となったユダヤ人たちのことをお話したことがあるが、戦争は終結し、捕虜解放のニュースが彼らの耳に届いた。グッドニュースである。しかし、そのニュースを聞いた彼らは、そんなことはあり得ないと信ぜず、振り向いて、囚人棟のある暗がりのほうに消えていったという。表情は暗い。足は逆向きである。エマオの途上の弟子たちも同じようであった。「主はよみがえられた」というグッドニュースを受けとめていない。だが同行者のみことばの説き明かしを通して変わって行く。32節で「道々お話くださる間、私たちの心は内で燃えていたではないか」とある。「燃える」と訳されていることばは、12章35節で「明かりをともしていなさい」の「ともす」と訳されていることばである。このことばは明るさとともに熱を意味させることばである。24章32節では熱に重きを置いた表現となっているが、いずれ、彼らの暗い心にみことばを通して光がともったと言っても良いだろう。そして夕闇の時間帯に、心の目が復活の主に完全に開かれたのである。主は夕暮れ時の光となった。
今日のエマオの途上の弟子たちの物語を読んで教えられることは、私たちの心の目が主イエスに開かれなければならないということである。私たちはみことばを通して主イエスを切に求め、「一緒にお泊りください」の信仰を持ち、私たちの心の目が生きておられる主イエスにはっきりと開かれることを願おう。キリストの臨在、キリストの顕現、キリストの現存を何よりも慕い求めて、みことばを通してキリストを知り、キリストを私の現実として歩んでいく私たちでありたいと思う。