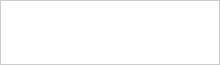前回は主イエスの葬りの物語を学んだ。前回の場面は23章56節、「それから、戻って香料と香油を用意した。そして安息日には、戒めにしたがって休んだ」で終わった。主イエスは金曜日に十字架につけられ葬られたが、金曜夕暮れから安息日ということで、安息日は遺体に何かをするということはなかった。けれども、その夜は悲しいお通夜という感じで、悲しみの夜を過ごしたはずである。そして24章1節で「週の初めの日の明け方早く」、すなわち、安息日が明けて日曜日の早朝、彼女たちは、準備しておいた香料と、また香油をもって墓に向かった。この日は亡くなって三日目ということだが、この三日目まで香料を塗ることをしたようである。また、この三日目が一番悲しみを表す日であったと言われている。だから、彼女たちは遺体にできるだけのことをしてあげようと遺体の処置に出かけただけではなく、泣きに出かけた。ところが、それは喜びに変わる。詩篇に「夕暮れには涙が宿っても、朝明けには喜びの叫びがある」(詩篇30編5節)とあるように。
まず墓に向かった女性たちは誰であったのかを確認しよう。10節を見ると、「それはマグダラのマリア、ヨハンナ、ヤコブの母マリア、そして彼女たちとともにいた、ほかの女たちであった」とある。数えると、最低5人になる。墓に2~3人で向かったような印象を与える紙芝居や動画があるが、墓に向かったのは最低5人はいたことを頭に入れておこう。彼女たちは23章55節によれば、「イエスとともにガリラヤから来た女たち」ということで、ガリラヤ伝道の時の女性の献身者たちである。筆頭には「マグダラのマリア」とあり、筆頭に挙げられているということで、彼女は篤信の女性であったことはまちがいない。彼女は8章2節では、「七つの悪霊を追い出してもらったマグダラの女と呼ばれるマリア」と紹介されている。彼女たちは夜どれだけ睡眠をとったのかわからないが、心は主イエスのことでいっぱいだったはずである。
彼女たちの一つの心配は墓に立てかけてある大きな石である。女たちでは転がせないような大きさである。それは男たちが転がすものである。では、男弟子たちにもついてきてもらえばいいじゃないかと言っても、墓には番兵たちがつけられていたことが他の福音書からわかる。彼らは石を封印していた(マタイ27章62~66節参照)。だから、人間的に考えてみると、石を転がしてくれる人などいるはずもない。ところが、「見ると、石が墓からわきに転がされていた」(2節)。実は、この「転がされていた」という文体は、神的受動態と言って、神によって転がされたことを意味している。神が転がしたということである。マタイ28章2節を見れば、その方法は御使いによって、ということである。
女性たちはラッキーと思って墓の中に入る。「そこで中に入ると、主イエスのからだは見当たらなかった」(3節)。墓には遺体がない。彼女たちの捜し方が足りないのではという話ではない。洞穴のスペースは限られている。そしてこの文章表現は、女性たちがまだ遺体を見つけてはいなかったという意味ではなく、見つからなかったという意味なのである。もうそこにはいない、ということを教える文章になっている。なぜ遺体はそこにないのか。墓が空であることは、それ自体が復活の強力な証拠になるというのではない。世の人々にとってはそういうことになる。誰かが盗んだのだろうとか、誰かが別の場所に移したのだろうとか、様々に言ってしまえる。実際は番兵たちがつけられていたので、そのようなことができるはずもないわけだが。墓が空であるというのは、それ自体で復活の強力な証拠ではないが、しかし信者たちにとって、それは復活を信じるに足りる証拠となったはずである。主イエスがご自身のよみがえりを告げておられたからである。けれども、彼女たちは復活を思い浮かべることはできない。訳が分からなくなって頭が混乱してしまう。どういうことなの?4節前半で「そのため途方に暮れていると」とある。「途方に暮れる」ということばは、「困惑する」「混乱する」という意味のことばである。
この頭がこんがらかってしまった状態に助けの手が差し伸べられる。それをするのが二人の御使いである。「見よ、まばゆいばかりの衣を着た人が二人、近くに来た」(4節後半)。この人たちは23節から御使いであったことがわかる。実は、二人の御使いが登場するのはこの場面だけではない。主イエスの昇天の場面で、やはり二人の御使いが登場している(使徒1章10節)。同じ御使いたちかもしれない。御使いたちは信者たちを諭し、正しい知識を与えようとしている。御使いたちのことばを二つに分けて見てみよう。「彼女たちは恐ろしくなって、地面に顔を伏せた。すると、その人たちはこう言った。『あなたがたは、どうして生きている方を死人の中で捜すのですか。ここにはおられません。よみがえられたのです』(5,6節前半)。御使いたちは主イエスのことを「生きておられる方」と呼んでいる。けれども、彼女たちの頭の中では、主イエスは死んだままである。死人である。この固定観念で頭はガッチガチになっていた。この固定観念が氷解するまでは今しばらく時間がかかる。御使いたちは、はっきりと事実を告げる。「ここにはおられません。よみがえられたのです」。主イエスは墓の中にはいない。いる必要もない。死人ではないからである。主イエスはよみがえられたのである。
御使いたちは、そう言っても混乱したままであろう彼女たちに、みことばの約束に心を留めさせようとする。それが次のことばである。「またガリラヤにおられたころ、主がお話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人たちの手に引き渡され、十字架につけられ、三日目によみがえると言われたでしょう」(6節後半,7節)。主イエスは生前、ご自分の死と復活について三回は話されていた。私たちも確認してみよう(9章22節,9章44節,18章32,33節)。最初の二つがガリラヤでのおことばである。主イエスは三日目によみがえるということを、はっきりと話されていた。けれども、彼女たちの心は鈍く、その音声しか聞いていなかった。それで、死んでいる、死んでいると、頭が凝り固まってしまっていた。御使いたちは今、もう一度主イエスのことばを繰り返し語ることにより、そういえばそうだったと、思い出させようとしている。
彼女たちはどうなっただろうか。「彼女たちはイエスのことばを思い出した」(8節)。彼女たちはこの時、思い出したのであって、完全に信じたわけではない(ヨハネ20章参照)。けれども彼女たちは思い出させられたことによって、信じるほうに傾いていったことはまちがいない。人は容易に復活を信じるところまでたどり着けないことは確かである。それは男弟子の反応を見てもわかる。
彼女たちは、「そして墓から戻って、十一人とほかの人たち全員に、これらのことをすべて報告した」(9節)。彼女たちは墓に出かけて見聞きしたことを報告した。10節にあるように、多数の女性たちの証言であるから、それは信じるに値するのに、なんと、「この話はたわごとのように思えたので、使徒たちは彼女たちを信じなかった」(11節)。「彼女たちを信じなかった」と、復活を信じる信じない以前に、彼女たちの話が信用できなかった。墓が空であったとか、御使いたちが現れ復活を口にしただとか、彼女たちの話が作り事に思えた。だが、彼女たちが全員口裏を合わせてlこのような作り話をする意味はあるのだろうか。だいいち、彼女たちは遺体に香料を塗ろうとして墓に向かったわけだから、復活に心が向かうわけはない。また全員が全員、催眠術にでもかかってしまい、一つの物語を吹き込まれたのだろうか。そんなことも考えられない。だが、男弟子たちにとって彼女たちの話はたわごとにすぎなかった。「たわごと」を協会共同訳は「馬鹿げたこと」と訳している。教会の土台となる使徒たちにとっても、復活物語は、最初は馬鹿々々しいものでしかなかった。だから、この世の人たちが、十字架についた人が救い主のはずはないだろうとか、復活なんて子どもだましみたいなことを信じられるかと反応しても、驚くにはあたらない。使徒たちでさえ、このような有様であった。主イエスが物わかりの悪い、心の鈍い弟子たちに対して忍耐してくださったことを覚えて、私たちも周囲の人々に対してそのような忍耐を身につけなければならない。
ルカはペテロの動きを付け加えている。「しかしペテロは立ち上がり、走って墓に行った。そして、かがんでのぞき込むと、亜麻布だけが見えた。それで、この出来事に驚きながら自分のところに帰った」(12節)。ペテロは主イエスを三度否認して丸二日ほどしか経っていない。ペテロの信仰はどうなってしまったのかと心配される状態にあった。主イエスを否認した後、表舞台からは遠ざかり、その後、十字架刑の時も含め、どこでどうしていたのかはわからない。そんな彼であったが、この時、他の使徒たちと一緒にいたということと、真っ先に立ち上がって墓へ走って行くという姿に、信仰はなくなっていなかったということがわかる。主イエスは最後の晩餐の席で、「わたしはあなたのために、あなたの信仰がなくならないように祈りました」(22章32節)と語ってくださっていた。
ペテロが走って墓に行ってみると、墓は空であった。神さまが墓の石を転がしたのは、空の墓というのを復活の一つの証拠として弟子たちに示すためであった。12節には「亜麻布だけが見えた」ということが付け加えられているが、そこにあるのは死人が身に着けていた亜麻布だけであった。主イエスのおからだは確かにない。この時ペテロは、彼女たちの話を信じただろう。だが、それは、主イエスはよみがえられたという明確な確信に至ったというわけではない。「この出来事に驚きながら」と、驚きが前面に表現されている。ここで「驚く」と訳されていることばは「不思議に思う」という意味のことばである(1章21節参照)。彼の反応は「驚く」「不思議に思う」で足踏みしてしまっている。空の墓を自分でも目撃して、女性たちの話を思い返して、もやもやスッキリ、ハレルヤ!主イエスはよみがえられた!とはならなかった。使徒のトップを行く彼でさえ、なかなか主イエスの復活を信じられなかった。彼は主イエスの口から復活の告知を直接聞いていたはずなのに。これが人間の性(さが)である。
今日の物語で心に留めたいのは、6節後半で、「まだガリラヤにおられたころ、主がお話になったことを思い出しなさい」と言われたことである。問われているのは、主が語られたみことばを信じるのかということである。復活された主イエスは、トマスに対して、「あなたはわたしを見たから信じたのですか。見ないで信じる人たちは幸いです」(ヨハネ20章29節)と言われた。今は見ないで信じることがあてはまる時代である。では見ないで何によって信じるのかというのなら、みことばによってということである。キリストの復活ということを、私たちはみことばによって信じた。私たちはみことばによって、私たちが罪赦され、神の子という立場が与えられたことを教えられている。また私たちは個別に、さまざまなみことばの約束が与えられることがある。みことばは真実である。それらを見失ってしまうと、私たちは浮き沈み激しく、ただの希望を失った人、ただの罪人として生きることになってしまう。
みことばを信じるために、聖書から一例を挙げよう。処女マリアである。「『神にとって不可能なことは何もありません』」。マリアは言った。『ご覧ください。私は主のはしためです。どうぞ、あなたのおことばのとおり、この身になりますように』」(ルカ1章37,38節)。田舎娘の処女マリアに、メシアとなる男の子が産まれるという御告げが御使いよりあった。それは一見、不可能なことであったので、御使いは「神にとって不可能なことは何もありません」と励ましを与えている。さて、この一文の直訳は、「神にとって、すべてのことばは不可能ではありません」となる。原文では「すべてのことば」とある。もちろん、それは、神が語られた「すべてのことば」である。神は御使いを通して、ご自身のことばをマリアに語られた。37節の「こと」の脚注を見ると、別訳として「語られたことば」とある。神が語られたことばはその通りなる。だから、マリアはそのことを受け止めて、「あなたのおことばどおり、この身になりますように」と言っている。この流れを心に留めていただきたい。マリアは御使いを通して聞いた神のことばを信じた。その通りになると。同じような信仰が私たちにも必要なのである。あなたのみことばは真実で、それは必ずその通りなりますという信仰である。
私たちが見失っているみことばはないだろうか。いや確かに、私たちは見失うことがある。だから日々、聖書に向かうのである。思い出させていただくという過程も経るのである。そしてそのみことばを「アーメン」と確信するまで、心に沁みとおらせるのである。そうするなら、曇った顔は晴れ、悲しみは喜びに変わり、弱々しい信仰の足は強くされ、前に力強く進むことができるのである。